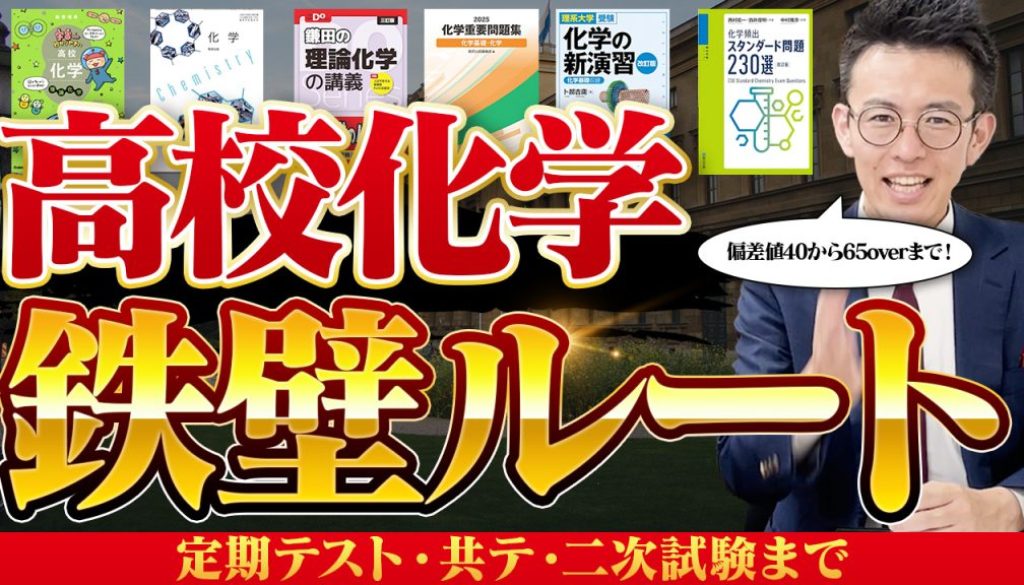【偏差値40から65overへ】化学参考書・問題集ルート&スケジュール|定期テストから受験まで
こんにちは。ラムス予備校の渡辺です。
化学は、生まれ持ったセンスに関係なく、努力と演習量をしっかりと確保すれば伸びやすい科目です。これまで努力してきたけれど、なかなか成績が伸びない、あるいは正しい勉強法が分からずに悩んでいる人でも、これからきちんとしたやり方を実践すれば、成績が伸びてくる可能性は高いです。
この記事では、化学の点数を爆伸びさせ、受験の得点源にするための、具体的な参考書、問題集の使い方、そして理想的な学習スケジュールについて詳しく解説します。
目次
Part 1:基礎固めとインプットのための参考書・教科書
参考書や教科書は、化学の基本的な考え方をインプットしたり、分からない時に立ち返って調べたりするための教材です。最初に知っておいてほしいのは、参考書にはレベル感があるということです。
1. 初学者・苦手な人向け参考書
-
宇宙一わかりやすい高校化学
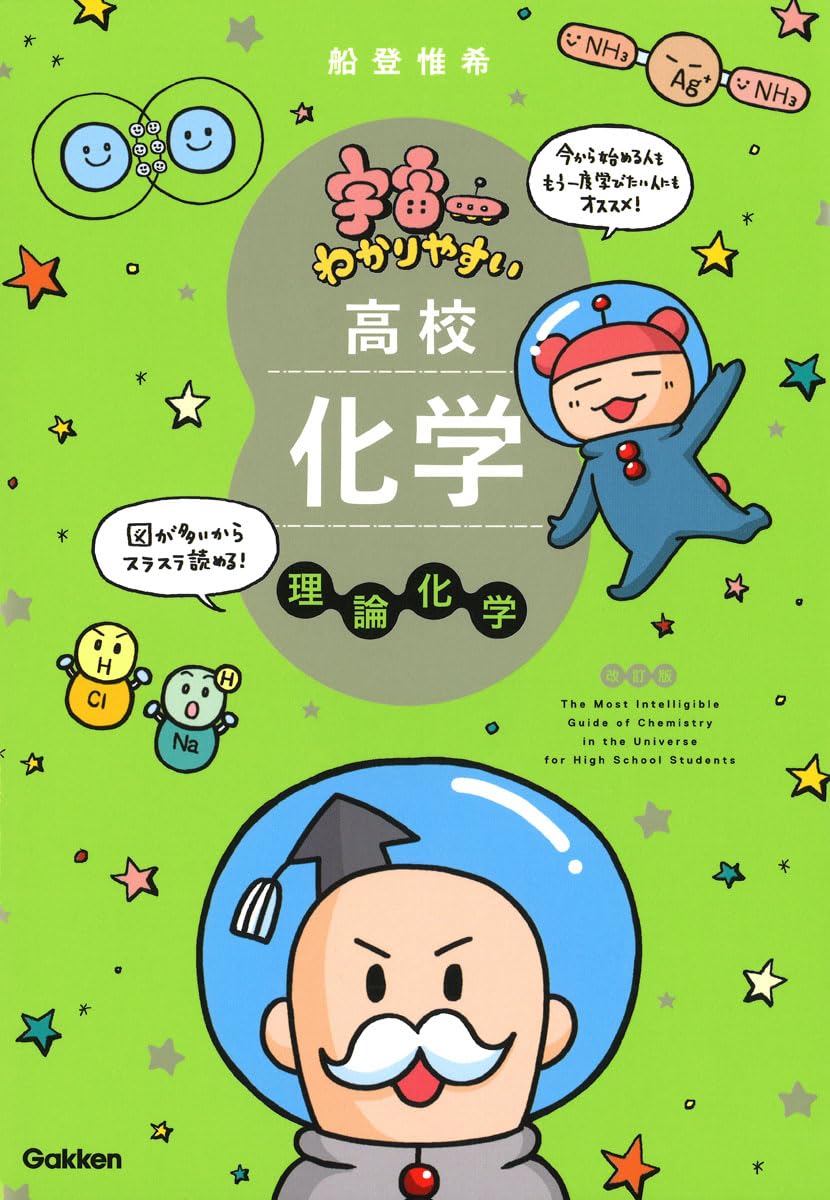
このシリーズ(理論編、有機編、無機編がある)は、教科書の硬い表現が苦手な人や、初めて化学を一から勉強する人に最適な参考書です。特徴は、左側のページに文字による説明があり、右側にそれに関するイラストの説明があることです。また、一定の部分が進むと、そこまで学んだことをチェックできる別冊の問題がついているのも非常に良い点です。
使い方としては、まず左側の文字情報で理解できるところまでしっかり読んでください。文字情報で理解できたならば、無理に右のページのイラストを理解する必要性はありません。イラストは、自分が文字情報で理解できない時に補助的な意味合いで活用してあげましょう。そして、必ず一定部分進んで「ここまできたら別冊へ」と書いてあるところに来たら、この別冊の問題をしっかりと解いてください。
『宇宙一』は、後に紹介するDoシリーズと比較して、受験に必要な知識を1から5または6までのように情報が絞られているイメージのため、初学者や苦手な人に適しています。
-
学校の教科書
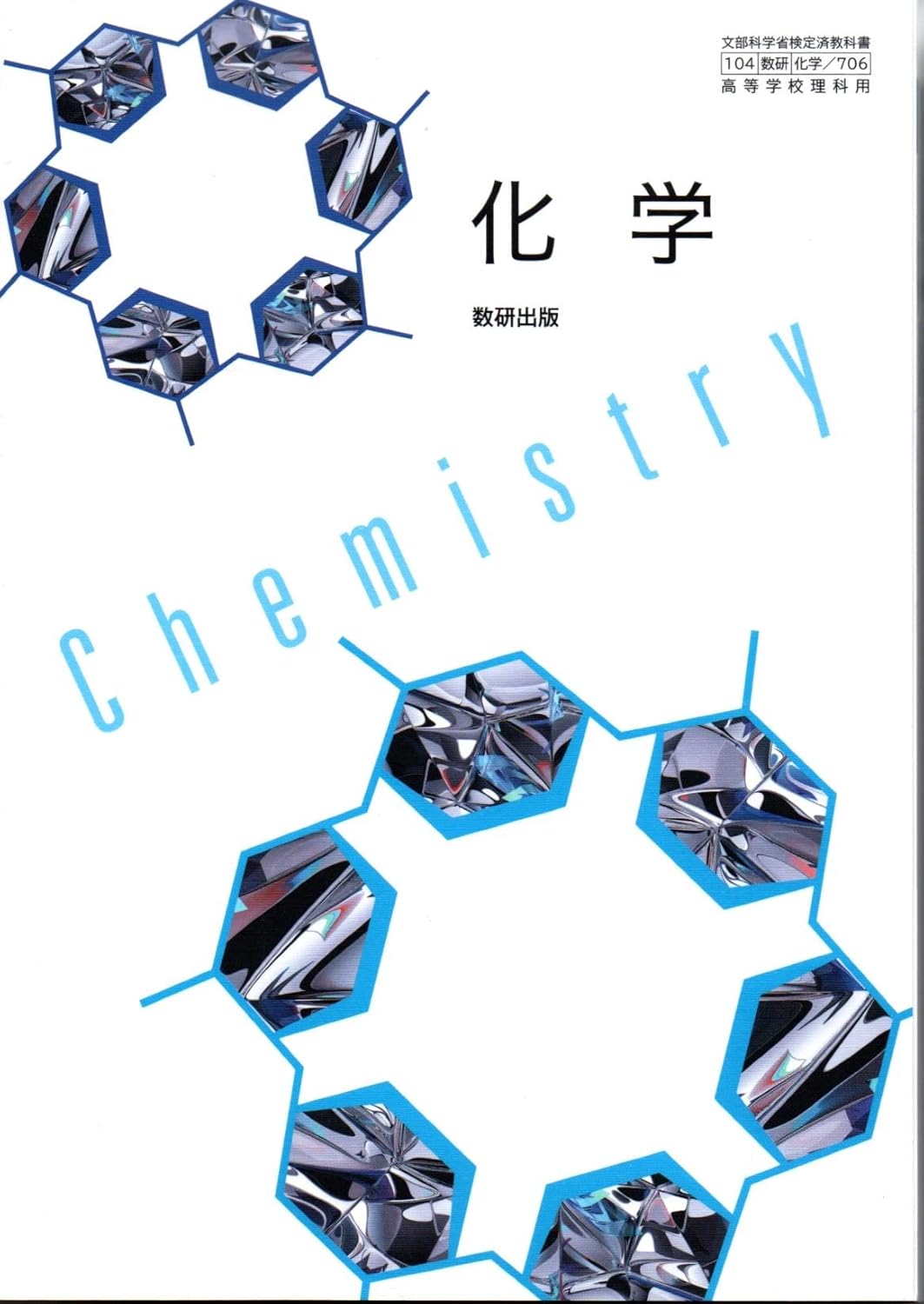
皆さんの手元にあるであろう学校の教科書は、学習指導要領に沿って作られており、必要な知識が網羅されています。また、共通テストも教科書に基づいて作成されているため、教科書をしっかりと読み込んで、言葉の定義等を確認することが重要です。ただし、教科書に硬すぎてアレルギー反応が出てしまう人もいるため、そういった人はまず『宇宙一』で読んでから教科書を読んであげると良いでしょう。
-
図説・図録
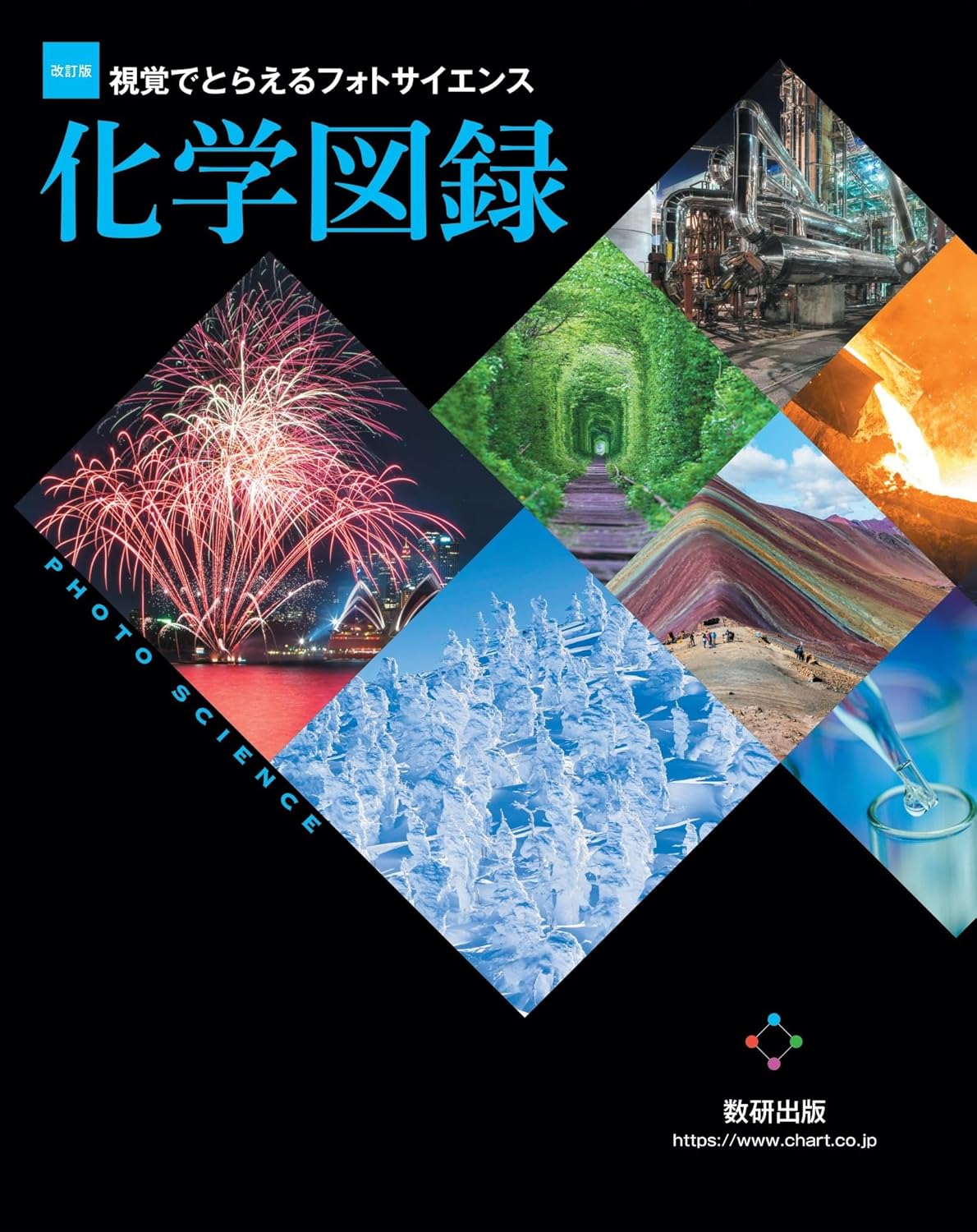
化学を初めて習う人や苦手な人など、視覚的なイメージで知識を補強したい時に、図説や図録を必要に応じて使ってあげてください。特に実験や無機の分野は、実際に目で確認したり、イメージがあった方が覚えやすいという人が多いため、化学の勉強ではマストな教材と言えます。最近の図説には、QRコードを読み込むと動画で見れるデジタルコンテンツが付いているものもあり、活用すると良いでしょう。ただし、全分野の図説を絶対に理解しなければいけないわけではありません。
初めて学習する人は、参考書として『宇宙一』か教科書、そしてこの図説が手元にあると良いです。
2. 中・上級者向け参考書(辞書・補強用)
-
Doシリーズ(理論化学のバイブル)
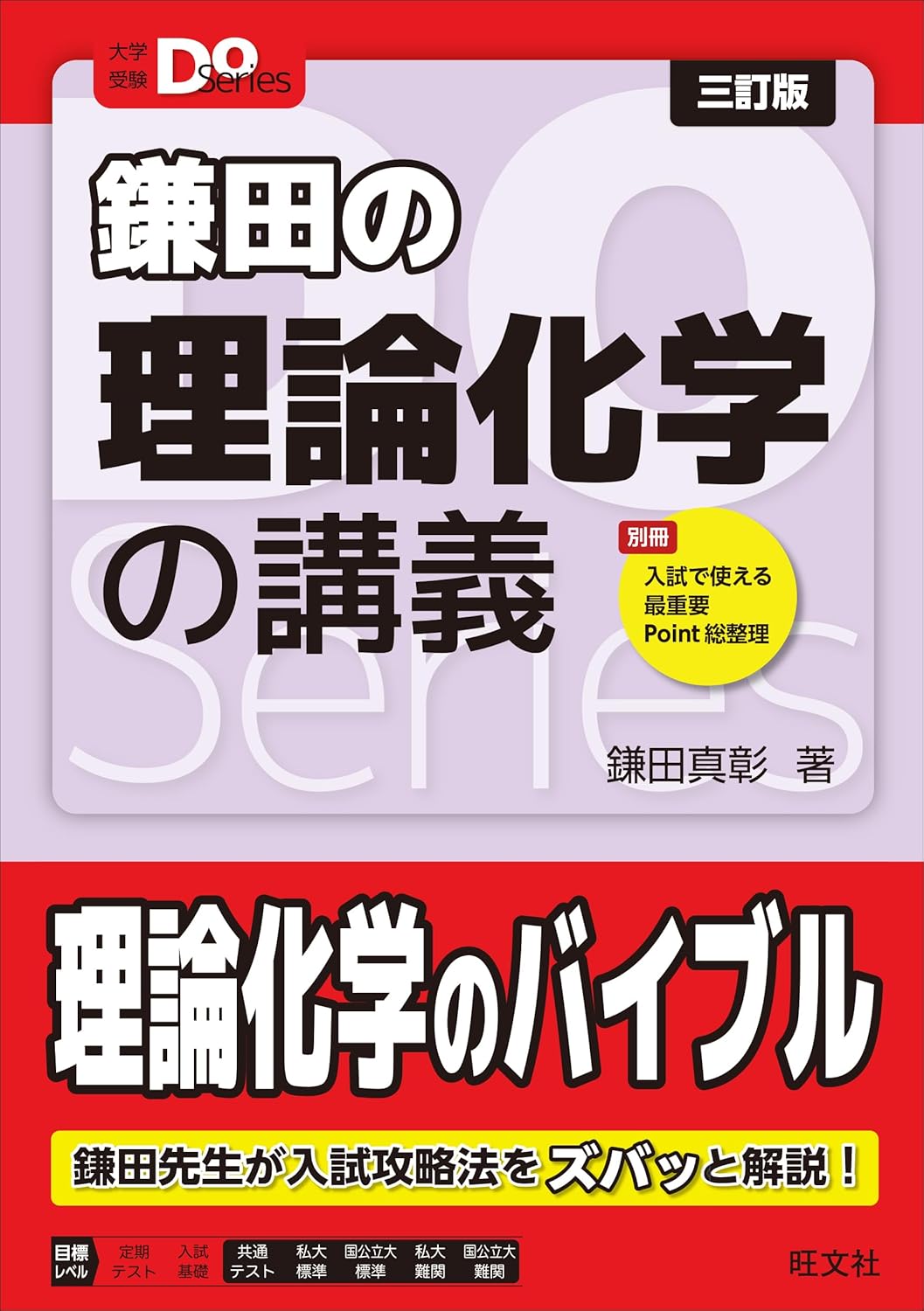
書店で「理論化学のバイブル」と書かれているDoシリーズですが、実際バイブルとして非常に良いものの、かなり中・上位者向けの参考書であると理解しておいてください。この参考書を使う目安は、河合塾の全答記述模試で最低でも偏差値60、できれば65ぐらいまで取れている人です。また、問題演習量で言えば、セミナー/リードα/重要問題集のA問題ぐらいまでしっかりと解けるようになっている人が使うと良いでしょう。
このDoシリーズは、受験の1から10まで全て網羅しているイメージであり、情報が絞られている『宇宙一』からある程度演習も踏んできて化学が得意科目になってきた人が進むべき教材です。
-
化学の新研究
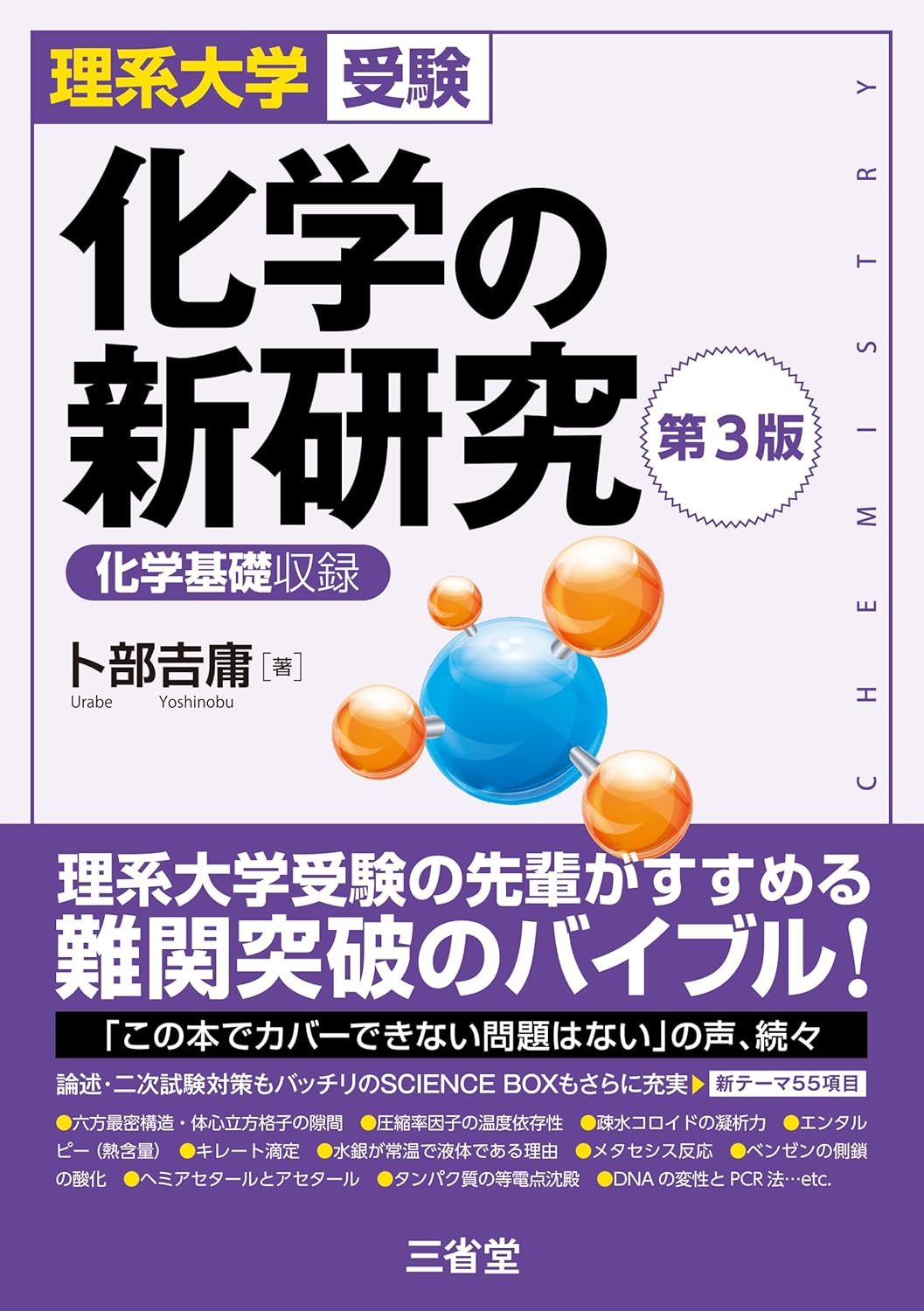
『化学の新研究』は、辞書的に使うための教材であり、これを一から読むということは基本的にはないと考えてください。偏差値が55〜60手前までは、分からないことがあれば『宇宙一』や図説で調べ、それでも分からなければ学校や塾の先生に質問するのが良いでしょう。
しかし、化学が得意になってきて(偏差値が60ぐらいまで)、自分で調べたい、ここ知りたいなという細かいことが気になり始めた人には、これで調べるのがオススメです。ただし、大学の内容など入試に不要な情報も含まれているため、これが入試で必要か、合格に理解が必要かを、必ず学校や塾の先生に確認しながら使いましょう。
Part 2:実力養成とアウトプットのための問題集ルート
化学の力をつけるためには、教科書などでインプットした知識を、問題演習によってアウトプットし定着させることが欠かせません。
1. 基礎の定着(偏差値55目標)
まず取り組むべきは、学校で配られるセミナーやリードα、あるいは書店で売られている化学の新標準演習といった問題集です。これらの問題集は、学校で習った内容を定着させるためのものです。
化学は定期テスト、入試どちらにおいても問題量が多いため、問題をじっくり読み込んで解けることも大事ですが、ある程度早く正確に解けることが求められます。早く正確に解けるようになるために、これらの問題集の基礎となる部分を繰り返し解いて、定石の処理を身に染み込ませる必要があります。
具体的には、セミナーであれば発展例題まで、リードαであればリードCぐらいまで、新標準演習であれば基本問題までをしっかりとやり込み、早く正確に解けることを目標としてください。いきなり応用問題に手を出すと、基礎が定着しない原因となります。
2. 受験の土台構築(偏差値60〜70目標)
上記の基礎問題集をしっかりやり込み、偏差値55を超えて、さらに上(60〜70)を目指したい人が取り組むべき問題集です。これらはどちらか一つをしっかりとやり込んでください。
-
重要問題集(重問)
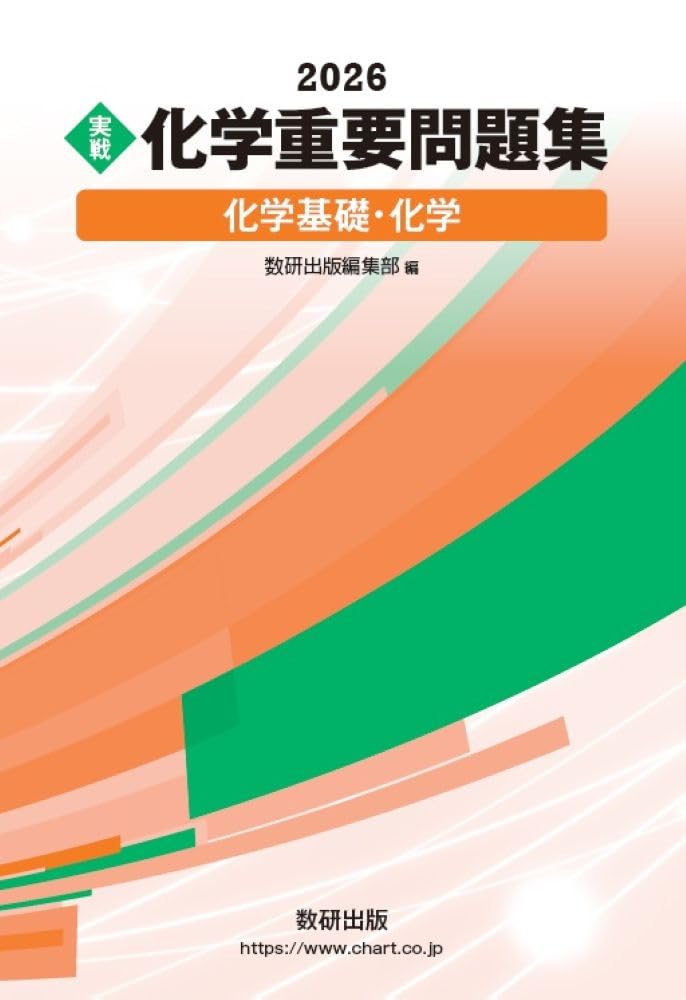
この問題集は、A問題とB問題にグループ分けされていることに加えて、「必解」(1回目に必ず解くべき)や「準マーク」(2周目に解くべき)といった問題のレベルや優先度がわかるようになっているのが特徴です。この重要問題集をどれだけやり込めるかによって、模試での偏差値は大きく変わってきます。中途半端にやると偏差値55で止まってしまうこともありますが、ラムス予備校の生徒の中には、これを2〜3周やるだけで河合塾の全答記述で偏差値70に到達した例もあります。
化学で重要なのは、難しい問題を解くことよりも標準的な問題を早く正確に解くことです。この重要問題集のレベルをとことんやり込むことで、東大・京大・阪大以外の旧帝大や、標準的な地方国公立医学部レベルまで対応が可能となります。
-
化学頻出スタンダード問題230選
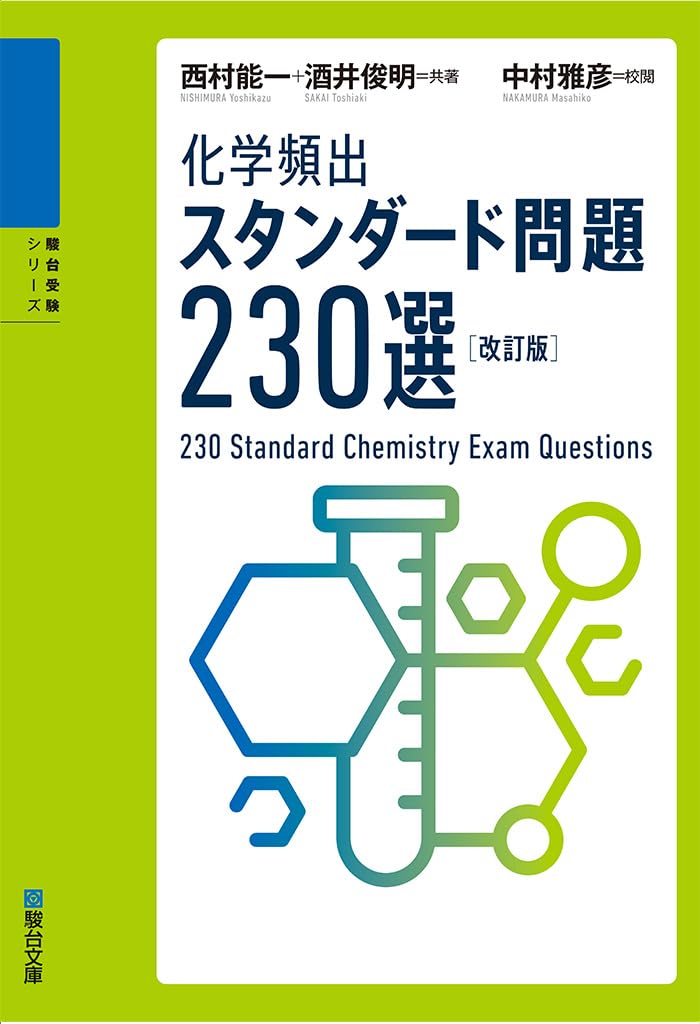
重要問題集の代替として推奨される問題集です。特徴は、問題の設問(小問)ごとに星1〜3のレベルがつけられており、非常に特徴的でやりやすい点です。問題数自体は230題で十分な量があり、学校でこちらを採用している場合は、このスタンダード230選をしっかりとやり込めば問題ありません。
3. 最難関大対策(偏差値65安定後)
東大、京大、阪大など特に化学が難しい大学を目指す人や、化学で圧倒的に差をつけたい人が、河合塾の全答記述模試で偏差値65ぐらいを安定して超えられるようになった後に取り組むハイレベルな問題集です。
-
標準問題精講
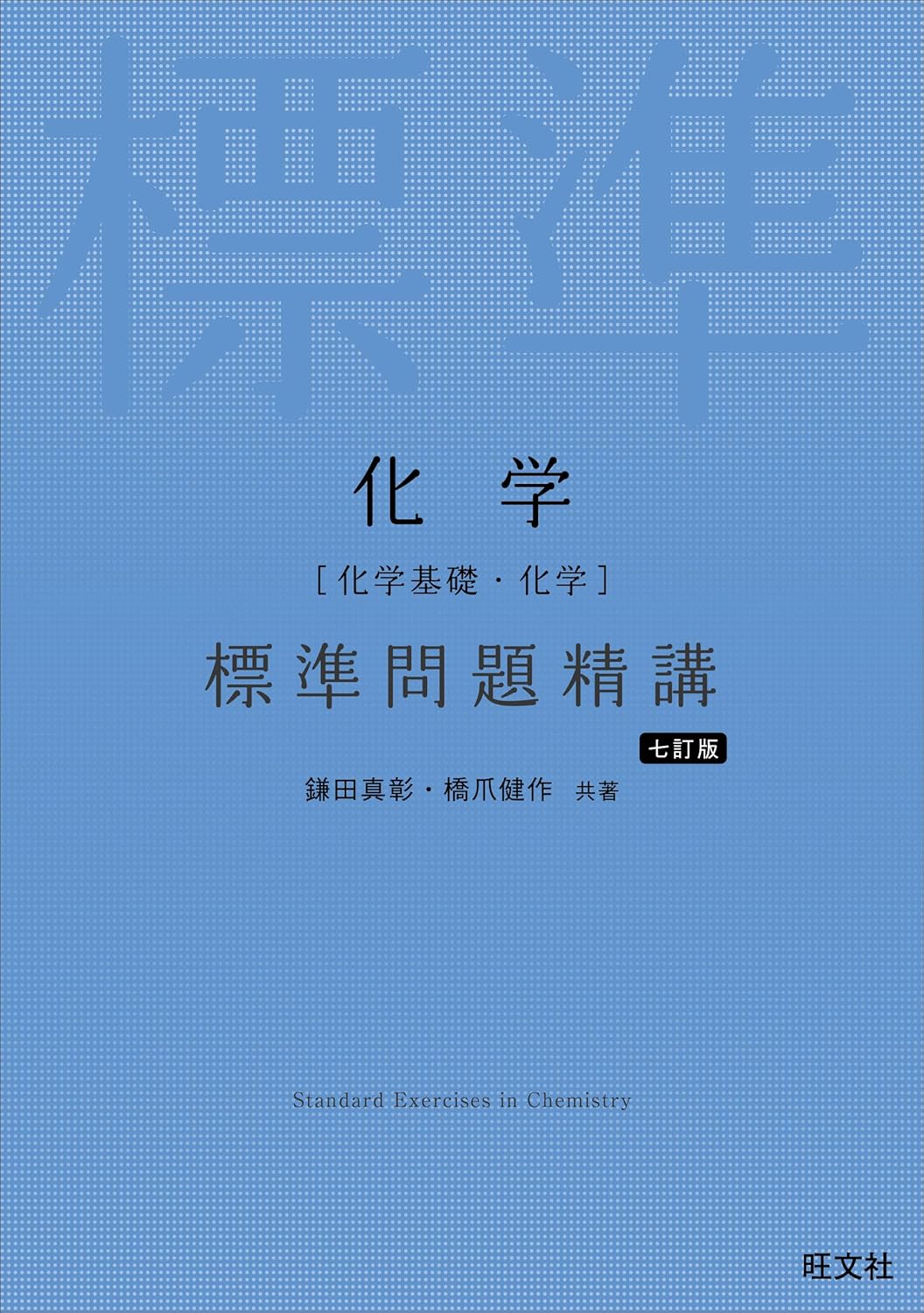
名前に「標準」と付いていますが、本当に難しい教材です。東大、京大、阪大といった最難関大学の二次試験にしっかり対応する土台をつけるための教材です。志望大学によっては不要な場合もあるため注意が必要です。
-
化学の新演習
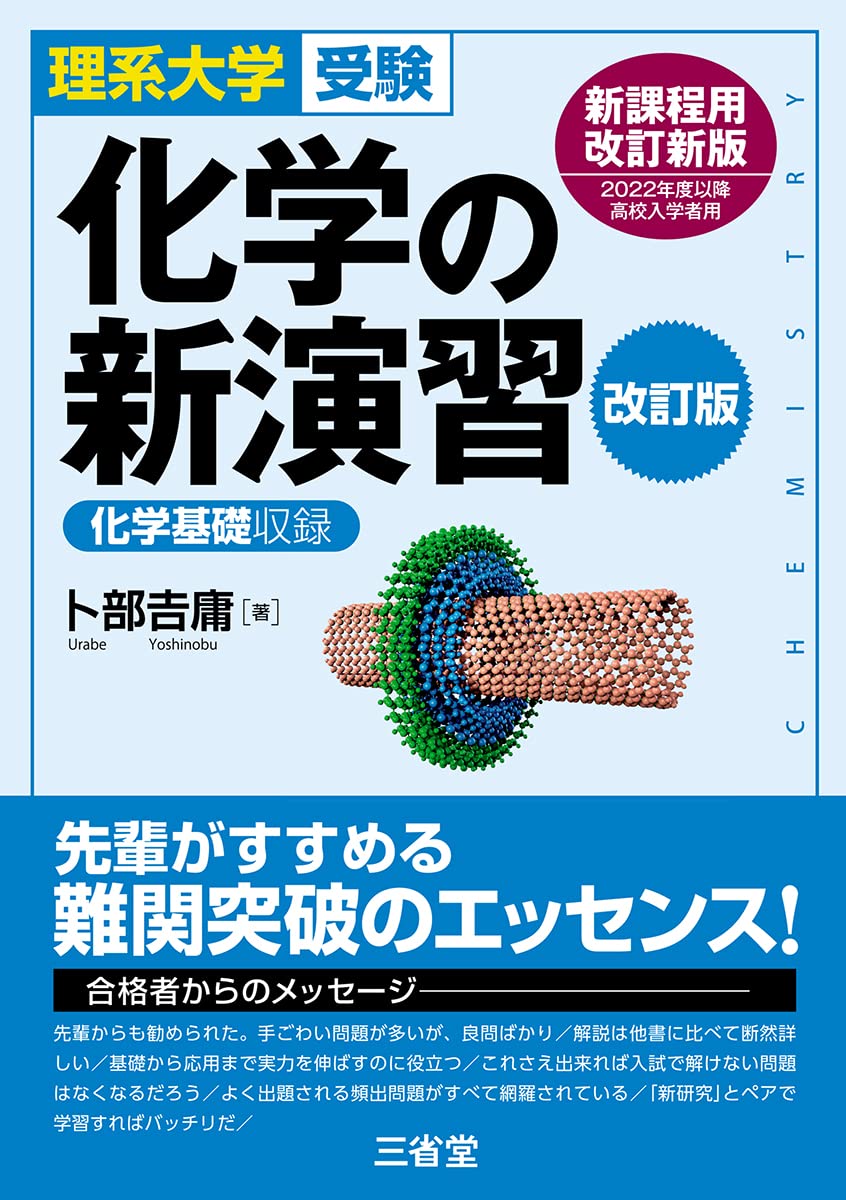
良書ではありますが、何より問題数が非常に多い(383題)のが特徴です。重要問題集やスタンダード230選よりも100題ほど多いため、特に現役生の場合はやりきれないという問題が発生しやすいです。使う場合は、残された時間や他の科目の仕上がりとの関係を考えて、頻出分野だけレベルを区切ってやるという使い方が効果的です。
-
駿台の有機化学演習
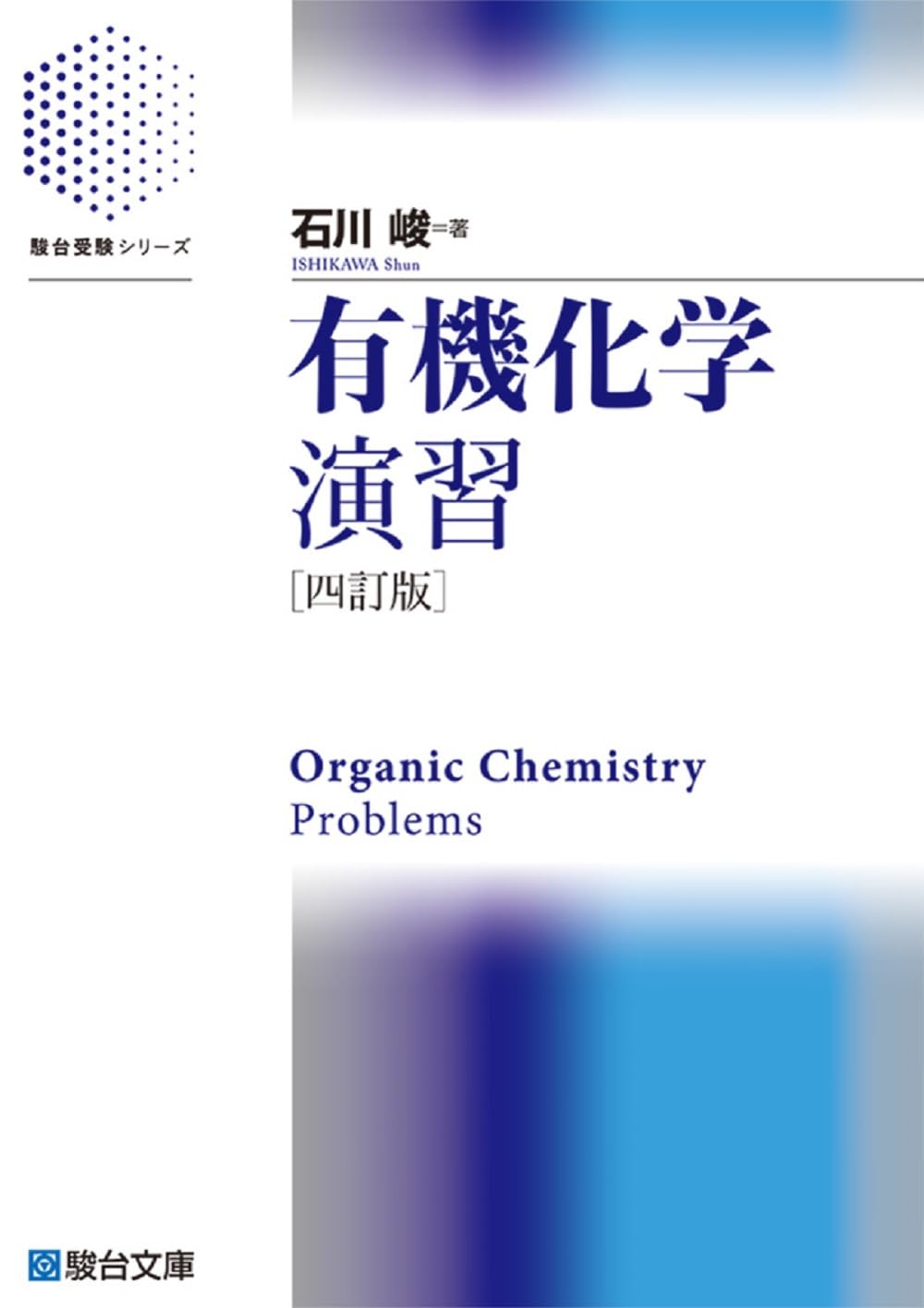
Version 1.0.0 有機化学に特化した演習で、二次試験で有機化学の出題の割合が高い大学の場合は使ってあげても良いでしょう。ただし、これらのハイレベルな問題集は、他の科目を優先すべき場面もあるため、着手する際は必ず学校や塾の先生に相談し、過去問や他科目を優先すべきでないか判断を仰いでください。
Part 3:共通テスト対策の進め方
共通テストの化学は結構難しいということを念頭に置いてください。どちらかというと、共通テスト用の問題集だけをやって高得点を取るというよりも、二次・私大向けの標準問題集(重問など)をしっかりやり込んだ上で、共通テスト用の問題集に取り組まないと高得点は取れない。
共通テスト形式の演習は、全分野を習い終わる高3の11月後半から12月に入ってからで大丈夫です。
-
チェック&演習化学(数研出版)
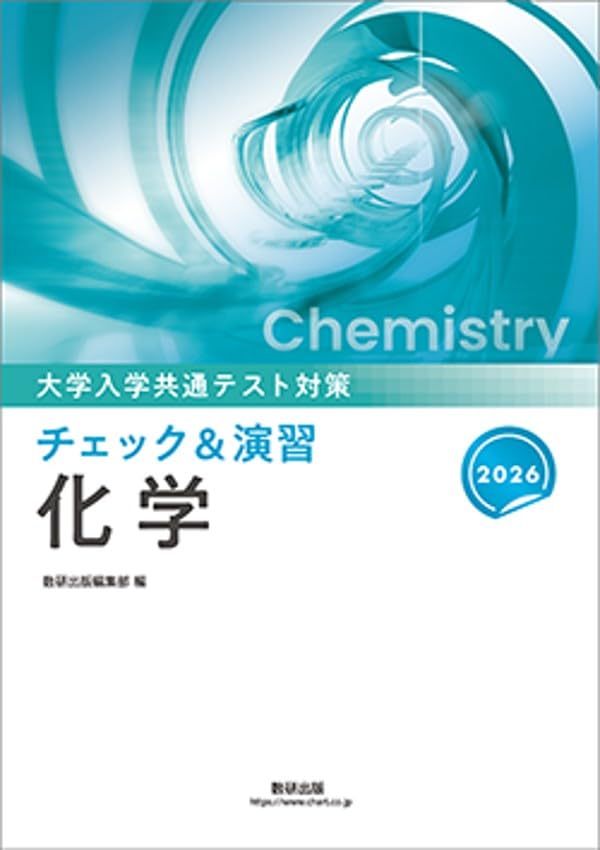
この問題集は、原則学校でしか買えません。もし学校で買うことができるならば、必ず買っておきましょう。特徴としては、センター試験や共通テストの過去問が分野別に配置されており、要点チェック、正誤チェック、重要演習、重要例題、編末演習とレベルがかなり細かく分けられています。また、問題ごとに解答目安時間が載っているのも使いやすい点です。重要問題集をやり込んだ後でこのチェック&演習をやり込むと、共通テストでも高得点が狙えます。
-
基礎マーク式の化学(河合塾)
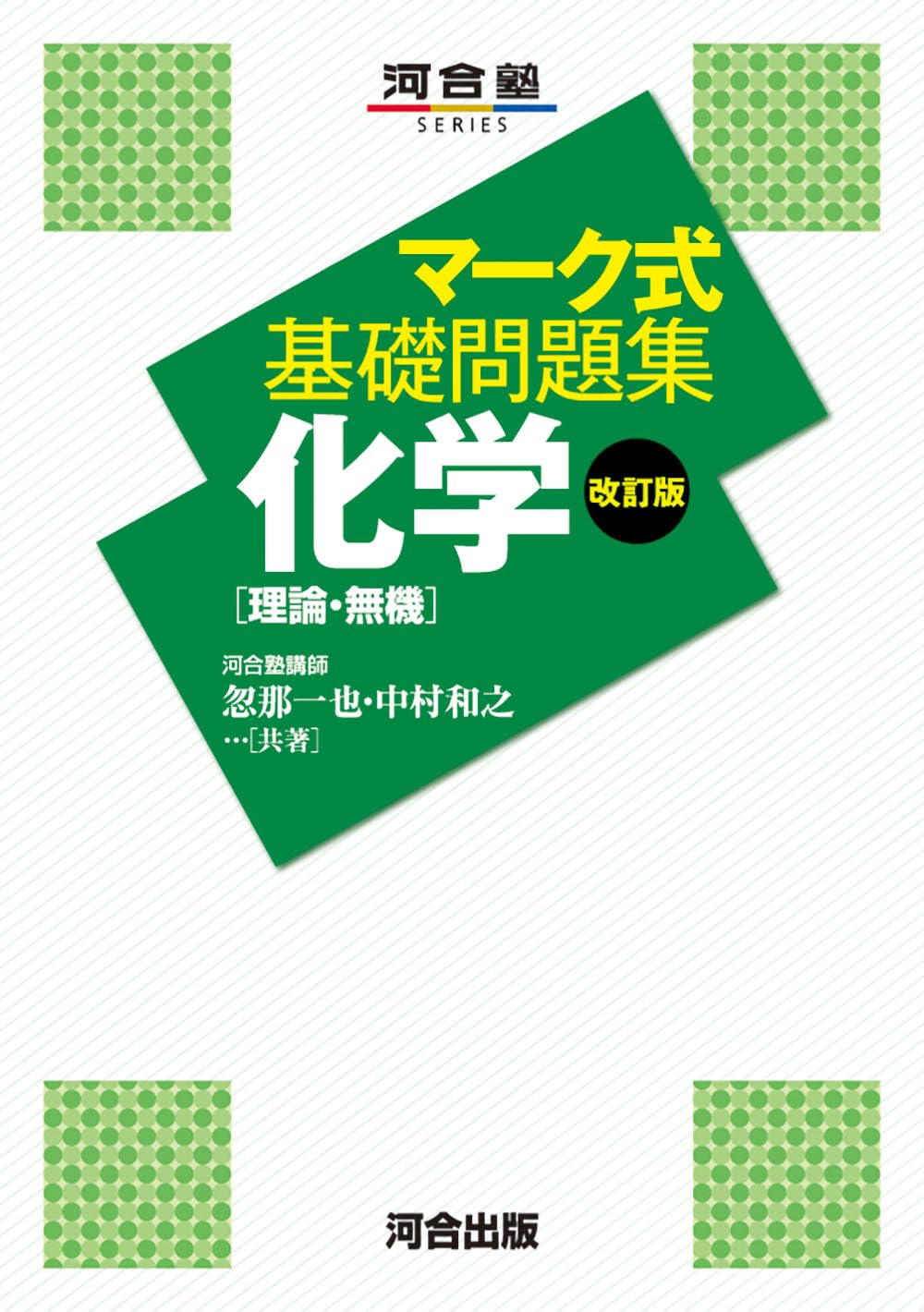
学校で『チェック&演習』を買うことができない人は、河合塾の『基礎マーク式の化学』を使ってください。これはあくまで基本・中級レベルであり、レベル設定はついていないので、全問しっかりと取り組むべきです。
-
短期攻略(駿台)
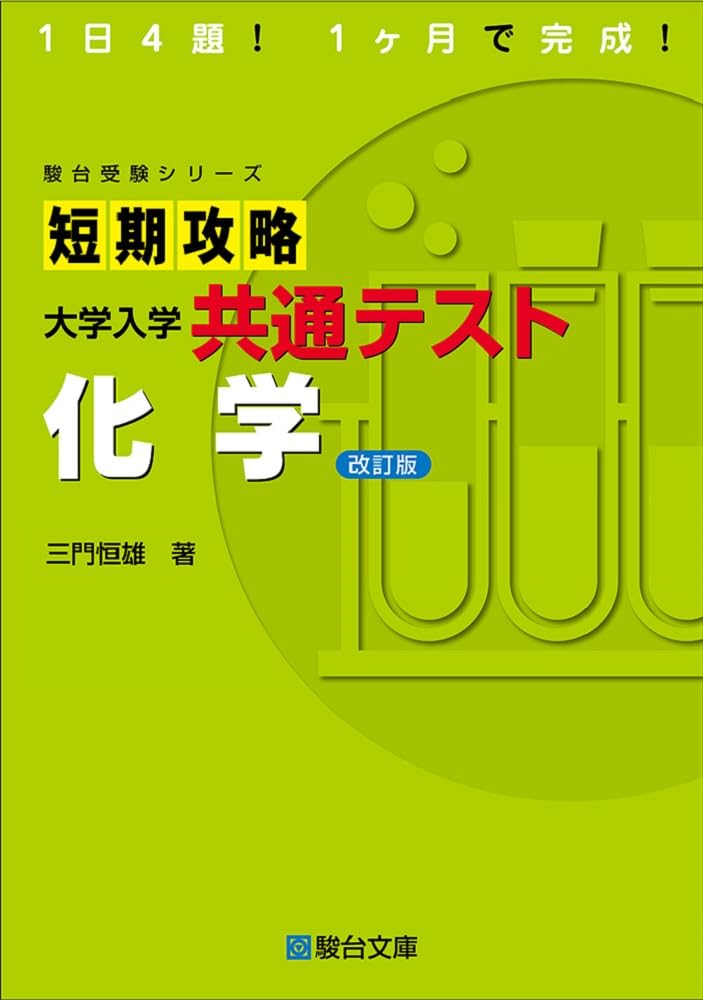
Version 1.0.0 『基礎マーク式の化学』がある程度できるようになった後で、もっと高得点を狙いたい人は、駿台の『短期攻略』を使いましょう。こちらは『基礎マーク式』よりも難しい教材です。星1から3でレベルが設定されているため、基礎マーク式からいきなりレベル3はきついという人は、まずはレベル2までをしっかりやるなど、レベルを意識して進めると良いでしょう。
-
共通テスト過去問演習
共通テストの過去問は、本試験を10年分程度やることを目標にしてください。追試験は本試験よりも難しいとされています。本試験で80点を安定して取れるまでは、繰り返しやり直したり、分野別問題集に戻って復習したりしましょう。
Part 4:【理想的な進路例】偏差値65を目指すスケジュール
現在の学力や志望校によってペースは変わりますが、ここでは河合塾の全答記述で偏差値65を目指すための理想的なスケジュール例を紹介します。
1. 基礎固めの徹底(定期テストと長期休暇)
リードαやセミナーなどのリードCまで、もしくは発展例題までを、定期テストごとに必ず仕上げてあげてください。さらに、長期休暇になったら、定期テストで入れた知識が劣化しないよう、そのリードCや発展例題までを2回目としてもう一度やり込み、グッと磨き上げて長期記憶に定着させましょう。
2. 受験勉強の土台作り(高2の冬休み〜高3の春休み)
この期間は、学校の授業で新しい内容(セミナーやリードα)を定着させつつ、既習範囲に関して、重要問題集のA問題全てに取り組んでください。やれるならば、B問題のうちの「準マーク」がついているものもやっていきましょう。これが受験勉強の土台作りになります。
3. 演習の強化と知識の完成(高3の春〜夏休み終わり)
高3の春からは、理論分野の2周目に入ります。セミナーやリードαが固まっていれば、重要問題集のA問題、Bの準マーク、それがやれていればBの準マークが付いていないものにも取り組みましょう。ただし、B問題をどこまでやるかについては、その時の化学の状況や学校の進度、志望校にもよるので、学校や塾の先生に相談してください。
無機化学については、夏休みの終わりまでに一周しておくことが理想です。有機化学については、学校の進度が遅いのではないかと予習すべきか迷う人が多いですが、これは理論・無機の完成度や学校の終了時期によってアドバイスが変わってくるため、必ず学校や塾の先生に予習するかどうかを含めて相談しましょう。
最重要目標として、高3の夏休み終わりまでに、既習範囲の重要問題集またはスタンダード230選のどちらかをとことんやり込むことが、偏差値65への近道です。
もし、このスケジュールに沿えない状況にある場合(例:高3の夏なのに化学が全然できない、重問までやったのに伸びない)は、個別で相談して原因を究明し、スケジュールやカリキュラムを組み直す必要性があります。
まとめ:ラムス予備校で最適な学習を
自分で「何を・どの順番で・どれくらい」やるかを決めるのは、実は一番むずかしいところです。 ラムス予備校では、今の成績・志望校・科目バランスを見て、あなた専用の勉強の進め方を一緒に決めていきます。 カリキュラムを配るだけでなく、「進め方」を伴走するので、1人で挫折しにくくなります。 「勉強のやり方があっているか不安」「相談できる人がいない」という方は、まずは無料相談・無料体験で話してみてください。